はじめに|いま、和紅茶が静かに熱い
近年、「和紅茶(わこうちゃ)」という言葉を耳にする機会が増えてきました。
これまで紅茶といえば、イギリスのアールグレイや、スリランカのウバ、インドのアッサムといった海外産の茶葉を思い浮かべる人が多かったでしょう。しかし、今あえて「国産紅茶=和紅茶」を選ぶ人がじわじわと増えています。
その背景には、味や香りの好みだけではない、日本ならではのストーリーや生産背景がありました。この記事では、和紅茶が注目されるようになった理由や、国産紅茶ブームの成り立ち、これからの可能性までを、初心者の方にもわかりやすく丁寧に解説します。
和紅茶とは?〜国産紅茶の定義と特徴〜
国産紅茶=和紅茶の定義
「和紅茶」とは、日本国内で栽培された茶葉を使用し、日本国内で製造された紅茶のことを指します。
緑茶と同じ茶の木(カメリア・シネンシス)から作られますが、製造過程で酸化発酵をさせることにより、紅茶となります。
和紅茶の特徴:やさしい味と香り
和紅茶の特徴は、なんといってもその「やさしい味わい」と「まろやかな香り」。
渋みが少なく、自然な甘みや花のような香りを感じるものが多く、ストレートで飲んでも飲みやすいのが魅力です。
コーヒーが得意でない人、刺激の強い紅茶が苦手な人でも「これなら飲める」とファンになることも多いです。
和紅茶が注目されるようになった背景
1. グローバル紅茶文化の中での「ローカル志向」
世界的に「ローカル×クラフト」の価値が見直されている今、日本でも「国産のものを選びたい」という動きが高まっています。
ビールやコーヒーと同じく、紅茶にも「地域ならでは」の個性を求める人が増え、和紅茶が注目されるようになりました。
2. 健康志向とカフェイン摂取の見直し
和紅茶は、緑茶よりもカフェインが少ない傾向にあり、刺激が抑えられています。
このため、子育て世代の女性や、午後にカフェインを控えたい人たちからの人気が高まっています。
また、日本人にとっては緑茶の親しみある香りと通じる部分があり、ほっとする「日本人の身体になじむ紅茶」として愛されてきています。
歴史から見る和紅茶の再評価
明治時代の紅茶輸出大国だった日本
実は、日本がかつて紅茶の生産・輸出国だったことをご存じでしょうか?
明治初期、日本は中国に次ぐ紅茶輸出大国でした。
静岡、鹿児島、熊本などで盛んに紅茶の生産が行われ、イギリスをはじめとする欧州諸国へ輸出されていたのです。
昭和の終わりと共に衰退した紅茶産業
しかし、輸入自由化や海外産の大量流通、国内需要の変化などを背景に、1980年代には国産紅茶の生産は激減。
多くの農家が紅茶づくりをやめ、茶畑は緑茶専用か、耕作放棄地になっていきました。
ブームの再来|2000年代からの復活
小規模生産者の挑戦
2000年代以降、地方の茶農家が、自ら紅茶製造に挑戦しはじめました。
その多くが、地域の活性化や6次産業化の一環としてスタートした取り組みで、クラフト的な手作り感や個性ある味わいが人気となり、各地で「地域ブランドの紅茶」が生まれていったのです。
SNSやクラフト系イベントでの広がり
マルシェやクラフト市、SNSなどを通して、和紅茶の名前やパッケージが可愛いと話題に。
「地域の紅茶って、こんなに美味しいんだ」と知った人々がクチコミで広げ、じわじわと和紅茶ブームが加速しました。
和紅茶の味わいの多様性
品種による違い
和紅茶に使われる品種は、大きく分けて緑茶向け品種と紅茶向け品種に分けられます。
- 緑茶向け代表品種:やぶきた、さやまかおり
- 紅茶向け代表品種:べにふうき、べにほまれ
同じ紅茶でも、やぶきたで作ると爽やかでほんのり甘く、べにふうきならコクがあり深い味わいになります。品種の違いで楽しめる風味の幅が、和紅茶の面白さです。
産地による違い
気候・土壌・標高などが違うことで、同じ品種でも産地によって味が変わるのも和紅茶の魅力です。
たとえば:
- 高梁紅茶(岡山):やぶきた使用。まろやかでほんのり甘い味わい。
- 嬉野紅茶(佐賀):花のような香りとすっきりした飲み口。
- 静岡の各地紅茶:さまざまな品種が試され、多様な味が楽しめる。
和紅茶を選ぶ人が増えている理由
理由1:パッケージやストーリーの魅力
手作り感のあるクラフトなパッケージや、生産者の顔が見える安心感は、ギフトにも喜ばれる要素です。
自分用だけでなく、お土産やプレゼントとして和紅茶を選ぶ人も多くなっています。
理由2:カフェイン控えめで飲みやすい
先にも述べた通り、和紅茶は渋みが少なく、飲みやすいのが特徴。
ストレートでも飲めるので、健康志向の方や、カフェインを控えたい午後の一杯として選ばれています。
理由3:生産者とのつながりや物語に共感
多くの人が、単に「飲み物」としてだけでなく、「物語」を重視するようになってきました。
地域の自然、作り手の想い、茶畑の再生など、和紅茶の背景にあるストーリーが、深く心に響きます。
和紅茶はこれからどうなる?未来の可能性
日本茶文化との融合
今後、和紅茶は緑茶と紅茶の文化をつなぐ「橋渡し的な存在」として位置づけられるかもしれません。
急須で淹れても美味しく、和菓子にも洋菓子にも合う、まさに“和”の中にある紅茶です。
カフェ・スイーツとのコラボも拡大
すでに東京や京都のカフェでは、和紅茶を取り扱う店も増えてきました。
今後は「和紅茶スイーツ」や「和紅茶ラテ」など、食とのコラボによってさらに広がりを見せるでしょう。
まとめ|和紅茶がもたらす「やさしさ」と「つながり」
和紅茶は、ただの国産紅茶ではありません。
そのやさしい味わい、地域に根ざした物語、生産者とのつながり。
それぞれが、わたしたちの暮らしに「一杯の豊かさ」をもたらしてくれます。
コーヒーに疲れた日。
子育ての合間に少し一息つきたいとき。
そんな時間に寄り添ってくれるのが、和紅茶です。
国産紅茶の新しいブームに、ぜひあなたも触れてみてください。

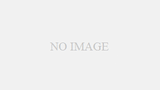
コメント