「和紅茶に興味はあるけど、どうやって作られるの?」
「実際に体験できる場所ってあるの?」
そう思っていた私が出会ったのが、高梁紅茶の紅茶づくり体験でした。
岡山県高梁市で開催されているこの体験イベントでは、実際の茶畑でお茶を摘むところから、萎凋(いちょう)・揉捻(じゅうねん)・乾燥といった紅茶づくりの工程を一通り体験できます。
ふだんは市販のお茶を飲んでいるだけの私が、ゼロから紅茶をつくるプロセスに触れることはとても貴重で、驚きと学びの連続でした。
今回は、そんな体験の様子と、紅茶づくりを通して感じた和紅茶の魅力を、エピソードとともにお届けします。
茶畑に一歩足を踏み入れて|お茶摘み体験
お茶の葉が育つ里山の風景
高梁市の山あいにある茶畑は、都会の喧騒とはまったく違う、穏やかで静かな空気に包まれています。
そこには手入れの行き届いた茶の木が整然と並び、朝露が光を反射してキラキラと輝いていました。
訪れたのは春の晴れた日。
ほんのり湿った空気と、若葉の香りが混ざり合った空間は、日常を忘れるような感覚を与えてくれました。
茶畑に足を踏み入れると、足元にはふかふかの土。
自然と呼吸が深くなり、心も体もほぐれていくようでした。
一芯二葉を手で摘む丁寧な作業
茶摘みは「一芯二葉」と呼ばれる、芽とそのすぐ下の二枚の葉を摘むスタイルで行います。
見た目以上に繊細な作業で、芽の硬さや葉の状態を見極めながら手で摘んでいきます。
講師の方に教えていただきながら、慣れない手つきで茶葉を摘むのですが、これがとても楽しい。
ふわっと手に伝わる葉の柔らかさや、摘んだ直後に漂う青々しい香りは、まさに生命を感じる体験です。
摘み進めるごとに少しずつコツが掴めてきて、「もっと摘みたい」と夢中になっていきました。
子連れでも楽しめる和やかな雰囲気
体験イベントには、親子で参加されている方も多く、和やかな雰囲気がとても印象的でした。
小さなお子さんが茶畑を駆け回りながら、お母さんと一緒に茶葉を摘む様子は、自然とのふれあいを通して家族の絆を深める貴重な時間になっているようでした。
茶摘みというとハードルが高く感じる方もいるかもしれませんが、実際は初心者にもやさしく、何よりも自然の中でリラックスできることが魅力です。
子育て中の方にもおすすめしたい、心がほっとする体験でした。
紅茶ができるまで|手づくりの醍醐味を学ぶ
萎凋(いちょう)で茶葉の香りを引き出す
茶摘みを終えると、すぐに紅茶づくりの作業に入ります。
まずは萎凋という工程で、摘んだ茶葉を風通しの良い場所に広げて水分を飛ばしていきます。
この工程によって、茶葉の香り成分がゆっくりと引き出され、紅茶らしい香りの土台ができあがります。
実際に広げた茶葉に顔を近づけると、最初とは違う、ややフルーティーで柔らかな香りが感じられて驚きました。
時間とともに香りが変化していく様子を見るのは、ちょっとした化学実験のようでもあり、飽きることがありません。
揉捻(じゅうねん)で紅茶らしい成分を引き出す
萎凋が終わると、次は茶葉を手で揉む「揉捻(じゅうねん)」の作業に入ります。
この工程では、茶葉の細胞壁を壊して酸化発酵を促します。
しっかり揉むことで、紅茶特有のコクや風味が生まれるのだそう。
手のひらで優しく、でもしっかりと揉んでいく作業は、思ったよりも力が必要でした。
葉の中からじんわりとエキスがにじみ出て、香りも一気に華やかさを増していきます。
作業中の手のひらには紅茶の香りが染みつき、いつまでも嗅いでいたくなるほど心地よかったです。
発酵・乾燥で完成へ|時間が作り出す味
揉捻を終えた茶葉は、一定時間発酵させた後、乾燥させてようやく完成です。
発酵の時間や温度は、茶葉の品種や天候によって調整される繊細な工程で、味や香りに大きく影響を与えるとのこと。
乾燥作業では、茶葉からしっかりと水分を飛ばし、長期保存にも耐えられる状態に仕上げていきます。完成した茶葉を見て、「あの青かった葉が、こんな紅茶になるんだ」と驚きと達成感がこみ上げました。
市販のお茶を飲んでいるだけでは気づけなかった、紅茶ができるまでの苦労と奥深さに触れた瞬間でした。
自分の手でつくった紅茶を試飲|味と香りの感動
一杯の紅茶が、こんなにおいしいなんて
完成した紅茶をその場で淹れていただく試飲タイム。
湯気とともに立ちのぼる香りは、市販のティーバッグでは味わえない、まさに手づくりのぬくもりを感じさせるものでした。
一口飲んでみると、口当たりはやさしく、渋みは穏やかで、ほんのりと甘みを感じる味わい。
今までの「紅茶」のイメージが覆された瞬間でした。
参加者の皆さんも「これ、自分で作ったの?」と驚きの表情。
自分の手で摘み、自分の手で揉んだ茶葉が、こんな味になるなんて——体験を通して味わう一杯の重みがまったく違うのです。
ほかの参加者との交流も魅力
試飲の時間には、自然と参加者同士の会話が生まれていました。
「どこから来ましたか?」
「お茶摘み、楽しかったですね!」
こういったやりとりから、和やかな交流の輪が広がります。
子連れの方、シニア世代のご夫婦、紅茶好きの若者など、さまざまな世代の人がこの高梁紅茶の体験を通じてつながっている様子がとても印象的でした。
紅茶が持つ「人と人をつなぐ力」を、体験を通して実感することができた瞬間です。
自宅で再現してみる|持ち帰った茶葉で再チャレンジ
茶葉とともに帰宅、さっそく再挑戦
体験終了後には、自分で摘んで加工した茶葉を少量ですが持ち帰ることができました。
せっかくなので、帰宅してからももう一度、乾燥や発酵の復習をかねて再挑戦してみることに。
自宅では気温や湿度の管理が難しく、同じようにはできませんでしたが、
それでも自分で淹れる一杯は格別。
家族にふるまってみると「これ、やさしい味でおいしいね」と言ってもらえ、うれしさがこみ上げました。
家で飲む紅茶の時間が特別になる
それまでは「ただ飲むだけ」だった紅茶が、自分で作ったという体験を通じて、毎日の中の特別な時間へと変わりました。
夕方、子どもが昼寝している間や、食後の静かなひとときに、そっと一杯淹れて飲む紅茶。
その一杯には、あの茶畑の風景や、手仕事の感触、香りの記憶がぎゅっと詰まっていて、ひとくちごとに心がほぐれていくのを感じます。
暮らしの中に和紅茶を取り入れることで、日常に小さな豊かさが生まれました。
高梁紅茶と地域のつながりを感じて
耕作放棄地から生まれた紅茶の物語
今回体験した高梁紅茶は、実はもともと耕作放棄地になっていた茶畑を再生して生まれた紅茶なのだそうです。
生産者の方から直接お話をうかがい、「この土地にまた命を吹き込みたい」という強い思いを知りました。
紅茶づくりは単なる加工ではなく、地域の未来を支える一つの営みなのだと知り、胸が熱くなりました。
日々の暮らしの中で紅茶を飲むという行為が、実は遠くの誰かの手仕事や土地の再生に結びついているという感覚は、これまでもったことのないものでした。
贈り物にしたくなる和紅茶
体験後、私はさっそく高梁紅茶を購入し、友人へのお土産にしました。
実際に贈った大分県の友人からは「ほんのり甘くてすごく飲みやすかった!また飲みたい」と、写真付きで感想が届いてとても嬉しかったです。
一緒に贈った地元のお菓子「神楽最中」との相性も抜群だったようで、「和のティータイムにぴったりだった」と好評でした。
和紅茶は、やさしい味わいだけでなく、物語のある贈り物としてもぴったり。
贈ることで地域の魅力も伝えられる、そんな嬉しい発見もありました。
まとめ|和紅茶は「体験すること」でより深く味わえる
今回の高梁紅茶づくり体験を通して、紅茶という飲み物の見方が大きく変わりました。
ただの嗜好品ではなく、手間をかけて育て、摘み、加工される中で、たくさんの人の想いが込められているものだということ。
それを実際に自分の手で体験し、自分の舌で味わうことで、和紅茶が「日常にある贅沢」へと昇華していきました。
子育て世代である私にとって、少しの自由時間に飲む一杯のお茶が、これほどまでに豊かで心を満たしてくれるとは思いませんでした。
高梁紅茶の体験は、そんな小さな「気づき」を与えてくれる素敵な時間でした。
和紅茶に興味がある方は、ぜひ一度、こうした体験に参加してみることをおすすめします。
きっと、あなたの紅茶時間が、もっと深く、もっとあたたかくなるはずです。

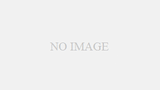
コメント